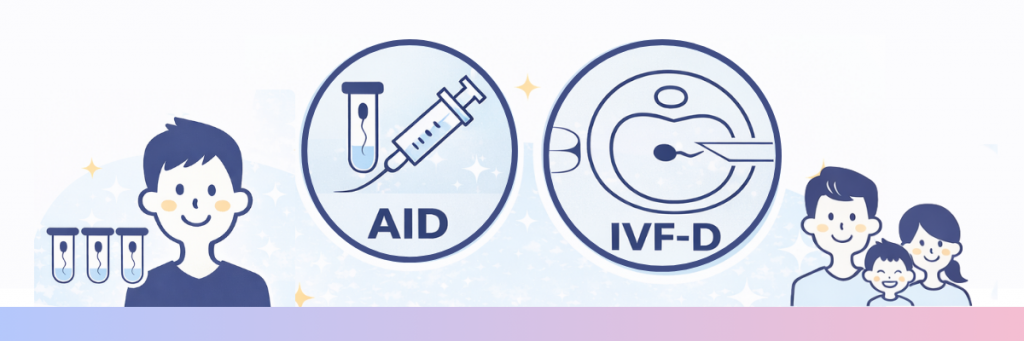
無精子症の方やトランスジェンダー男性(FtM)のご夫婦など、夫に精子がない場合には、第三者の提供精子を用いたAID(人工授精)やIVF-D(体外受精)という治療があります。当院は、日本産科婦人科学会に登録している、国内でも限られた認定施設のひとつです。
1.本治療の対象者
第三者の提供精子を用いたAID・IVF-Dの対象は、夫が無精子症、またはトランスジェンダー男性(FtM)である法律婚のご夫婦です。
- 提供精子が必要であると医師が診断しているご夫婦
- 妻が41歳まで、夫が47歳までに初診来院が可能なご夫婦
- 男性不妊や性別違和を受容し、告知を前提と考えているご夫婦(当院による支援あり)
※独身女性や同姓カップル、事実婚は本治療の対象ではありません。
2.まずは「勉強会」
第三者の提供精子を用いた治療について詳しく知りたい方、また当院での治療を検討・希望している方は、最初に【はじめてのAID・IVF-D勉強会】にご参加ください。この勉強会は、当院での治療をすすめるものではなく、倫理的に難しい側面もあるこの治療について、夫婦が十分に検討できるよう、情報を提供することを目的としています。
勉強会は原則として偶数月の第三木曜日に実施しており、毎回70人〜100人の方が全国から参加されています。お申し込みは、以下のバナーをタップしてください。
はじめてのAID・IVF-D勉強会3.AIDとは
AID(Artificial Insemination by Donor)とは、第三者の提供精子を用いた人工授精です。

AID治療の流れ
- 月経10-12日目頃|超音波検査などで排卵日を予測し、AID実施日を決定
- 月経13-15日目頃|AID当日、提供精子を融解し、妻の子宮内に注入。必要に応じて薬処方
- 遠方などの場合、排卵日予測は他の医療機関で行い、AIDだけを当院で実施することもできる
AIDの妊娠率・費用
- AIDの妊娠率は女性の年齢によって異なりますが、1回あたりおおよそ5~10%程度。妊娠に至った方では、1回目で妊娠するケースが最も多く、妊娠までに要した回数の平均は3.1回
- AIDの1回あたりの費用は、93,500円(税込)
4.IVF-Dとは
IVF-D(In Vitro Fertilization with Donor sperm)とは、第三者の提供精子を用いた体外受精です。AIDと異なり、体外で受精した受精卵を確実に子宮に移植することができることから、妊娠率が高いのが特徴です。

IVF-D治療の流れ
- 月経2-3日目|血液検査と超音波検査を実施し、卵巣刺激法を決定
- 月経9-11日目頃|卵胞の発育を確認し、採卵日を決定。卵胞の発育が不十分な場合は再来院
- 月経12-15日目頃|採卵当日、採卵手術を行い、卵子と提供精子を顕微授精する
- 受精卵を移植し、約10日後に妊娠判定を行う
※IVF-Dの前には、IVF-D説明会と倫理委員会による審査があります
IVF-Dの妊娠率・費用
- IVF-Dは、提供精子による良好性から、夫婦間体外受精よりも妊娠率が高く、流産率が低いのが特徴。妊娠率は、33歳までは57%以上、34-36歳は54%以上、37-39歳は45%以上。妊娠に至った方では、1回目で妊娠するケースが大部分
- IVF-Dの採卵から胚移植1回目までの合計は、約45万(受精卵が少ない場合)から90万円くらい。凍結する受精卵の数によって費用に幅があり、凍結数などは夫婦が決められる
5.出自を知る権利
本治療の3原則
- この治療により生まれる人の出自を知る権利に配慮した仕組み
- 「告知」はこの治療の基本
- この方法で家族になった当事者を孤立させない。具体的で、継続的な支援
ドナーの情報開示
当院は、日本で唯一、子どもの出自を知る権利を最優先とした仕組みをもつ医療機関です。
| AID | IVF-D | |
|---|---|---|
| 匿名性 | 匿名 | 非匿名*1 |
| ドナーのプロフィール*2 | 妊娠後の夫婦に開示 | 妊娠後の夫婦に開示 |
| ドナーの病歴 | 妊娠後の夫婦に開示 | 妊娠後の夫婦に開示 |
| 成人した子とドナーの接触 | 不可能 | 可能 |
| 近親婚の確認*3 | 可能 | 可能 |
*1 成人した生まれた人と接触(メール・手紙・電話・会う)のいずれか1回以上を実施できるドナー *2 ドナーの身長・体重・身体の特徴・血液型・趣味特技・職業・精子を提供する理由・親のルーツ *3 結婚相手が同じドナーから生まれた人ではないことの確認
当院から夫婦・子どもへの支援
当院の夫婦や生まれた人への支援プログラムは、受診前から、生まれた後も、その先も、切れ目のない支援を目指しています。
①当院を受診する前
- 対面で4時間の勉強会を開催
- 妊娠する方法に目が向きがちな夫婦に対して、その前に考えておくべきことを整理
- 医師、臨床心理士、当事者の先輩から、それぞれの立場でお話
②当院を受診してから
- 学習教材を通したワーク
- カウンセリングや面談
- 夫婦の告知計画書作成まで支援してから治療を開始
③妊娠した後
- 妊娠20週頃、臨床心理士またはソーシャルワーカーから、ドナーの周辺情報と病歴を夫婦へ開示
- 子どもへの告知のセリフを一緒に検討
④妊娠中から出産したあと
- 告知に役立つ、「絵本作成会」を開催
- 家族で参加できる「親子会」を開催
- 子どもが成人するまでの間、治療患者様と同じ費用で何度でもカウンセリングを受けられる
⑤生まれた人への支援
- 15歳以上を対象とする「子ども会」を開催予定
- 成人した後は、当院に対して、近親婚の確認ができる
- 非匿名ドナーの場合、成人した後は、当院を仲介した接触ができる
6.AID・IVF-Dの費用
無精子症・FtM(AID・IVF-D)の費用7.治療までの流れ
-
- 時期
- 偶数月の第3木曜日
- 概要
-
- 第三者の提供精子を用いた治療について詳しく知りたい方、また当院での治療を検討・希望している方は、最初に【はじめてのAID・IVF-D勉強会】にご参加ください
- この勉強会は、当院での治療をすすめるものではなく、倫理的に難しい側面もあるこの治療について、夫婦が十分に検討できるよう、情報を提供することを目的としています
- 関連ページ
-
- 時期
- 勉強会のあと・いつでも
- 概要
-
- 「勉強会」参加後、ご夫婦で十分に話し合ってください
- 当院での治療を希望される場合は、勉強会後にお送りするメール内の【AID・IVF-D初診登録】からご登録ください
- 登録後、提出書類の案内が自動送信されます。必要書類を準備のうえ、当院へご提出ください
- 書類到着後、2週間以内に初診予約のご案内をお送りします(不備がある場合はご連絡します)
-
- 時期
- 初診日
- 概要
-
- 初診予約日は、ご夫婦そろってご来院ください
- 持ち物は、初診予約時にご案内します
- 初診日は、説明・検査・診察を行い、所要時間は約2〜3時間です
- 初診日に、学習教材をお渡しします
-
- 時期
- いつでも(夫婦のペースで進める)
- 概要
-
- 初診時にお渡しした学習教材をもとに、ワークを進めてください
- ワークシートが完成したら、当院へご提出ください
- 提出後、カウンセリングの予約をおとりください
- 進め方や時期に期限はありません。ご夫婦のペースで進めてください
-
- 時期
- カウンセリングから21日以内
- 概要
-
- 倫理委員会申請前カウンセリング実施後、カウンセリング報告書および提出書類を当院から倫理委員会へ提出します
- 倫理委員会にて、本治療を行うことについてご夫婦の承認可否を審査します
- 審査結果は、21日以内にメールまたは書面でお知らせします
-
- 時期
- 承認後いつでも
よくあるご質問
-
回答
AID・IVF-Dについて検討している方、当院を受診したい方は、最初に「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。勉強会では、精子提供に伴う倫理的な課題を踏まえ、その上で幸せな家族をつくる方法について、丁寧にお話ししています。勉強会にご参加いただいたからといって、必ず治療を進めなければならないわけではありません。むしろ、じっくりと検討していただくための場として設けております。
-
回答
精子提供の人工授精(AID)、体外受精(IVF-D)の料金はこちらをご覧ください。精子提供の治療は、保険適用外のため、自由診療になります。
-
回答
法的に婚姻している夫婦で、男性が無精子症や、性別変更により、精子がなく、第三者の精子提供以外に妊娠の方法がないと医師が判断した方です。なお、独身女性(選択的シングルマザー)や同性カップルへの治療は、当院では実施していません。
-
回答
はい、第三者の提供精子を用いたAID・IVF-Dでは、ご夫婦そろって勉強会への参加が必須となります。本治療は、子どもの権利に関わる大きな倫理的課題を含むため、当院では子どもの権利を最優先に考えた治療を行っています。勉強会では、治療に進むにあたってご夫婦に準備していただきたいことや、向き合っていただきたい課題について詳しくご説明します。また、提供精子でお子さんを授かり、告知を行いながら子育てをしている先輩パパのお話を聞いていただいたうえで、治療を検討していただきたいと考えています。
-
回答
提供精子を用いた不妊治療は、日本産科婦人科学会の規定により、法律婚の夫婦に限って認められています。その背景の一つとして、日本には「精子ドナーは父親ではない」と明確に定めた法律がないことが挙げられます。このため、独身女性や同性カップルが提供精子で子どもを持った場合、患者本人とドナーの間で同意があっても、ドナーに扶養義務などの法的責任が生じる可能性があります。また、生まれる子どもとは事前に治療に関する契約を結ぶことができないため、法的に親子関係が明確になる法律婚の夫婦に限定して、提供精子による治療が認められています。
-
回答
当院の精子ドナーの平均年齢は34.2歳です。ドナーは、精液検査・DFI検査・感染症検査・染色体検査に加え、心理検査(MMPI-3)、面談、家族歴の確認など、複数のスクリーニングを受けています。そのため、ドナーの採用率は約30%です。ドナーは自らの意思で「匿名提供」または「非匿名提供」を選択しています。いずれの場合でも、子どもの出自を知る権利への配慮のため、妊娠後にご夫婦へ、ドナー個人を特定しない範囲の情報を提供しています。これは、親から子どもへの告知(テリング)に活用していただくためのものです。なお、非匿名ドナーの場合は、子どもが18歳以上になり、本人が希望した場合に限り、ドナーとの接触が可能です。
-
回答
多くの方が、最初は告知の具体的な方法が分からない状態から検討を始められます。当院では、初診前に行う勉強会に加え、初診後は「告知が家族にとってどのような意味を持つのか」を考えるための教材やワークシートをご用意しています。それらに取り組みながら、告知の考え方や進め方を整理していきます。その後、臨床心理士によるカウンセリングを受けていただき、その内容をもとに倫理委員会で確認を行います。告知に向けた準備が整っていると判断された場合に、治療を開始します。
-
回答
はい、可能です。精子提供の治療については、まず「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。勉強会で本治療の要件や考え方について情報を共有した後、個別相談をご希望の方は、臨床心理士によるカウンセリング(対面・オンライン)をご利用いただけます。ご予約は受診前にお電話(03-3356-4211)にて承ります。
-
回答
AID・IVF-Dの対象、必要書類、治療の流れ、費用、子どもの権利などについては、「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。医師・当事者・心理士から、より詳しくお話ししています。
-
回答
はい、当院では妊娠・出産後も、お子さんが18歳になるまで継続的な支援を行っています。主な支援内容は以下のとおりです。
① ドナー情報開示:妊娠後は、ソーシャルワーカーおよび臨床心理士が、ドナー個人を特定しない情報を開示し、お子さんへどのように伝えていくかを一緒に考え、支援します。
② 当事者同士がつながる場:絵本作成会・親子会・子ども会の3つの活動を通じて、当事者同士がつながり、支え合える場を大切にしています。
③ 18歳までの継続相談:お子さんが18歳になるまで、治療中の患者様と同じ料金で、心理カウンセリングを何度でもご利用いただけます。
④ 近親婚回避の確認:AID・IVF-Dで生まれた方が18歳以上になった際、結婚相手が同一ドナー由来ではないかの確認を、当院を通じて行うことができます。
⑤ 非匿名ドナーとの接触:非匿名ドナーによる治療で生まれたお子さんは、18歳以上になり、本人が希望した場合に限り、当院を介してドナーとの接触が可能です。